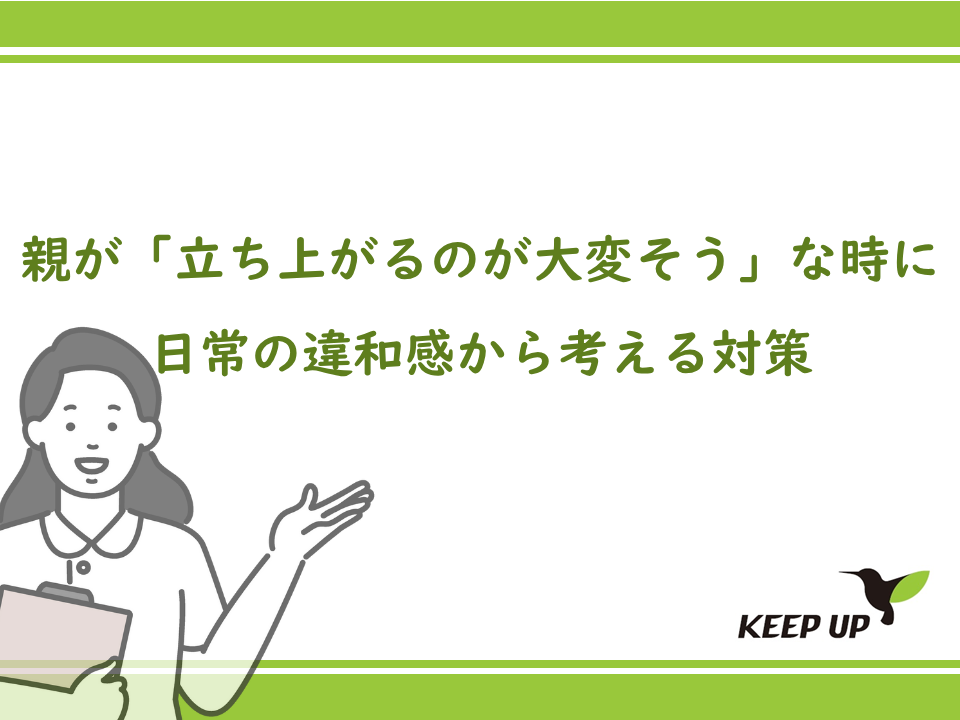最近、実家に帰ったときにふと目にした光景。
「お母さん、立ち上がるのに時間がかかってるな」「お父さん、いったん手をつかないと立てないみたいだ」
——こうした小さな違和感を覚えたことはありませんか?
理学療法士の視点から言えば、「立ち上がり動作の困難」は、筋力やバランス能力の低下だけでなく、将来的な転倒リスクや介護予備軍への移行の兆候である可能性があります。
気づいた今が、その「違和感」に向き合うチャンスです。
◎「立ち上がり」に必要な機能とは?
立ち上がり動作は、実は全身を使う高度な動きです。
特に重要なのは、以下のような身体機能です。
- ・大腿四頭筋(太ももの前面の筋肉)
- ・臀筋群(お尻の筋肉)
- ・体幹の安定性
- ・足関節の柔軟性やバランス機能
これらのうち一つでも弱くなると、「立ち上がりが遅くなる」「途中でふらつく」「勢いをつけないと立てない」といった変化が見られるようになります。
実際、加齢とともに大腿四頭筋の筋力は年に1〜2%ずつ低下するといわれています。
また、筋力が低下すると、椅子からの立ち上がりに必要な床反力を十分に得られず、バランスを崩しやすくなります。
(Frontera WR et al., 1991)
○「違和感」がサインである理由
たとえば理学療法士が医療の現場で多くの患者さんに接していると、「転んでから来院する」方が非常に多いのが現状です。しかし、転倒のリスクはそのずっと前から日常に現れています。
「最近、親が立ち上がるときに「どっこいしょ」と言っている」「一度うつむいて息を整えてから動いている」など、小さな変化が先行サインです。
実際、立ち上がり動作の所要時間が延びることは、**フレイル(加齢に伴う身体的脆弱状態)**の指標のひとつとされています。
たとえば、「5回立ち座りテスト(Five Times Sit to Stand Test)」では、15秒以上かかると下肢筋力低下やバランス不良が疑われます。
(Bohannon RW, 2006)
○対策は「鍛える」だけではない
「じゃあ筋トレをすればいいのか」と考える方も多いですが、ポイントは日常生活に組み込むことです。
1.立ち上がりの工夫
まずは椅子の高さを見直しましょう。
座面が低すぎる椅子は立ち上がり動作を困難にし、膝や腰への負担も大きくなります。
適切な椅子の高さは、膝の高さと同じかやや高めが理想です。柔らかすぎるソファーも立ち上がりにくくなることがあります。
運動学的には、足を手前に引いて、椅子に浅く腰掛けてから立ち上がるだけでも、重心移動距離が短くなり、立ち上がり易くなります。
2.「ながら筋トレ」
テレビを見る前に5回、立ち座りを繰り返す、台所で煮物を待つ間につま先立ちを10回、というように、日常動作に筋力トレーニングを組み込むことで、運動のハードルが下がります。
3.体調チェックも忘れずに
立ち上がりがつらい原因は筋力だけではありません。
膝関節症や脊柱管狭窄症、起立性低血圧、抑うつ症状など、医療的な背景が潜んでいることもあります。
動作だけでなく、顔色や動作後のふらつき、疲労感にも注目してみてください。
○「立ち上がるのが大変そう」は、将来へのヒント
親の立ち上がりに違和感を感じたら、それは「まだ間に合うサイン」です。
見過ごさず、一緒に運動を始めたり、かかりつけ医や理学療法士に相談することで、将来の転倒や要介護状態を防ぐ可能性が高まります。
理学療法士として強く感じることは、「家族のちょっとした気づき」が最良の予防策になるということです。
◎終わりに
「立ち上がりがつらそう」という日常の小さな違和感は、未来への大きなヒントです。
親が自分らしく、安心して日常生活を送れるよう、今こそ行動を始めましょう。
――それは、介護予防の第一歩であり、親への最大の思いやりかもしれません。
References:
・Frontera WR, et al. (1991). Aging of skeletal muscle: a 12-yr longitudinal study. Journal of Applied Physiology.
・Bohannon RW. (2006). Reference values for the five-repetition sit-to-stand test: a descriptive meta-analysis of data from elders. Perceptual and Motor Skills.