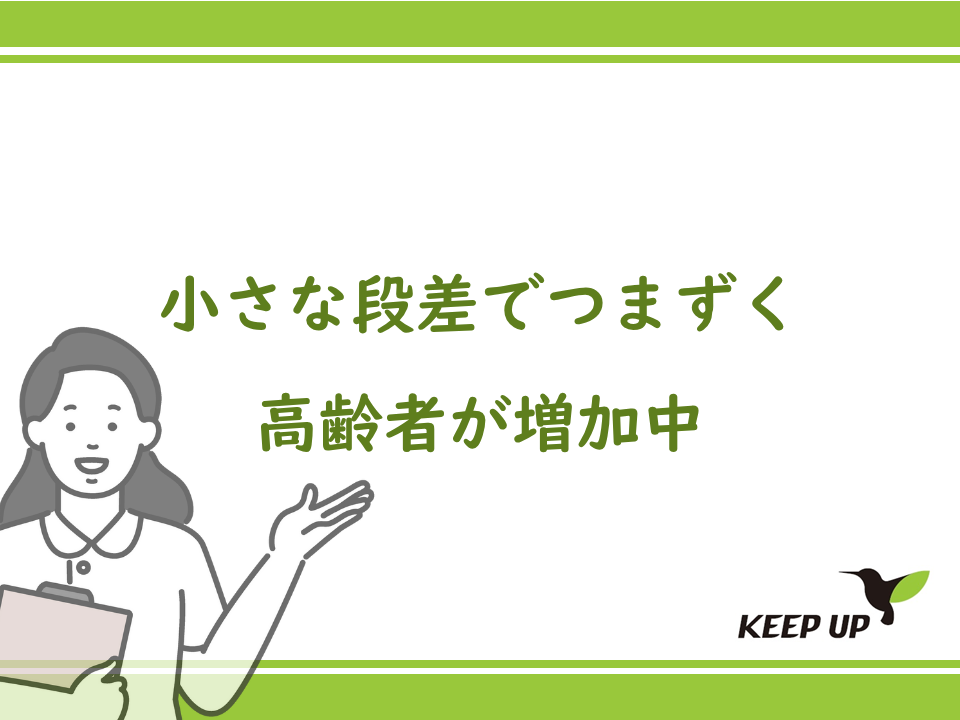「最近、親が玄関の段差につまずいた」「絨毯の端に足を引っかけて、ヒヤッとした」
——そんなエピソードを耳にする機会が、理学療法士として年々増えています。
実際、厚生労働省の報告によれば、高齢者の事故原因の中で最も多いのは「転倒・転落」であり、全体の約7割を占めています(※1)。
その中でも、「ちょっとした段差」でのつまずきは、日常生活のなかで見落とされやすい危険ポイントです。
◎なぜ小さな段差でつまずくのか?
加齢によって足腰の筋力や関節可動域、バランス感覚が少しずつ低下していくことは、誰にでも起こりうる自然な変化です。
しかし、それに気づかず、以前と同じ感覚で動いてしまうことが、転倒につながる大きな原因となります。
特に注目すべきは「足の持ち上げ方」が変化すること。
加齢により大腿四頭筋や腸腰筋といった股関節を持ち上げる筋力が低下し、歩行時に足がしっかり上がらなくなります。すると、玄関の框(かまち)や敷居、カーペットの端など、数センチの段差につまずいてしまうのです。
さらに、視覚や深部感覚の衰えにより、床の段差に気づきにくくなることもあります。
視力低下や白内障、暗がりでの見えにくさなどが重なると、「段差の存在に気づけない」ことがリスクを高めます。
○家庭内で注意すべき場所
家庭内で特に転倒リスクが高い場所としては、以下のようなポイントがあります。
- ・ 玄関の段差や上がり框 : 靴を履く動作と段差の昇降が重なり、バランスを崩しやすい
- ・ 和室の敷居 : 数センチの段差でも高齢者には負担になる
- ・ 絨毯・マットの端 : 足が引っかかりやすく、滑りやすい素材もある
- ・ 浴室と脱衣所の段差 : 濡れて滑りやすいうえ、足元が見えにくい
- ・ 階段 : 手すりがない、段差が一定でないなどで危険度が上がる
これらはすべて「家庭のなかで起こる事故」であり、環境を少し整えることで大きくリスクを減らすことが可能です。
参考リンク:転倒を予防していつまでも元気に 理学療法士ハンドブックhttps://www.japanpt.or.jp/activity/asset/pdf/handbook18_whole_compressed.pdf
○転倒予防のために家庭でできること
高齢者の転倒は、そのまま「骨折」や「寝たきり」へとつながりかねません。
だからこそ、未然に防ぐ対策が重要です。以下は、家庭でできる簡単な予防策です。
1.環境の工夫
- ・ 段差にはスロープや段差解消マットを設置
- ・ 床のマットや絨毯は滑り止めをつける、もしくは撤去
- ・ 玄関や階段に手すりを取りつける
- ・ 夜間には足元を照らす常夜灯を活用
2.関節の変形や痛み
- ・ ふくらはぎや太ももの筋力を保つ簡単な体操を日課に(例:椅子に座っての足踏み運動)
- ・ バランス能力を養う片脚立ち(※安全な場所で、支えのある状態で実施)
3.靴の見直し
- ・ 室内でも滑りにくく、つまずきにくい靴を使用
- ・ かかとをしっかり支える履物を選ぶ
4.家族や地域との連携
- ・ 転倒が不安な場合は地域包括支援センターに相談し、住宅改修の助成制度などの活用を検討
- ・ 必要に応じて理学療法士による訪問指導や評価を受けることも効果的
◎理学療法士の視点から伝えたいこと
私たち理学療法士は、筋力やバランス機能の変化を数値や動作の分析を通して評価し、その人に合った運動や環境調整を提案できます。
「歩きにくくなった」「つまずきが増えた」など、些細な変化が見られたときは、早めに専門家に相談することで、将来的な転倒や介護状態の予防につながります。
また、地域包括支援センターとの連携により、必要な支援や福祉用具の導入、住宅改修制度の利用についても、きめ細かなアドバイスを行うことが可能です。
地域のなかで支えあいながら、安心して暮らせる環境を一緒に整えていきましょう。
※1:厚生労働省「令和4年 高齢者の事故に関する報告書」より