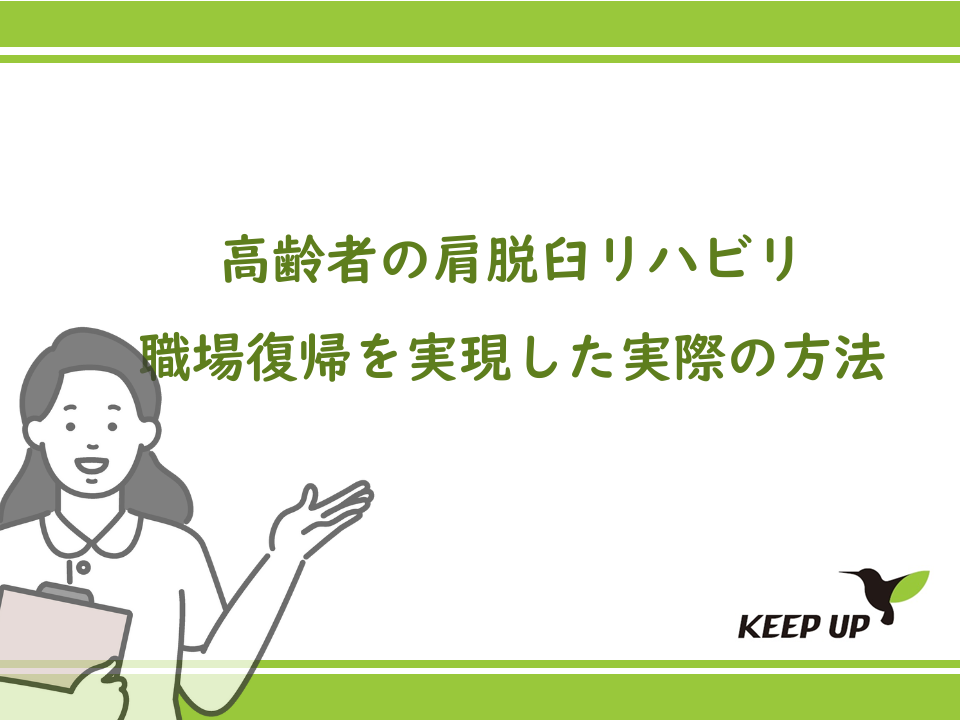肩関節の脱臼は、高齢者にとって重大な機能障害をもたらします。
特に加齢に伴う筋力の著しい低下や骨・靱帯の脆弱化は、脱臼後の回復を大きく妨げる要因となります。さらに「また外れるのではないか」という恐怖心から上肢を使わなくなり、急速に廃用が進んでしまうケースも少なくありません。
しかし、適切なリハビリを行えば「痛みの軽減」「関節安定性の回復」「筋力再建」を通じて、日常生活のみならず社会活動への復帰も可能です。
ここでは、私が研究・教育で取り組んでいる視点を踏まえ、高齢者が肩脱臼後に職場復帰を果たした症例を紹介し、理学療法士が果たすべき役割について解説します。
◎高齢者の肩脱臼リハビリ:特有の3つの課題と専門的なアプローチ
1.筋力の著しい低下:脱臼により腱板x筋群(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)や三角筋が弱体化し、腕を持ち上げる力を失いやすい。
2.再脱臼の不安:外旋や外転といった危険肢位を避けるあまり、動作が極端に制限される。
3.生活および社会活動の制限:服の着替えや整容が困難になるだけでなく、職業上の動作(パソコン入力、軽作業、対人対応など)が阻害される。
これらの問題に対しては、人体解剖学と障害特性を熟知した理学療法士による個別対応が不可欠です。
○症例紹介:70代男性、肩脱臼後の職場復帰
背景
対象は70代前半の男性。地域の工房で軽作業を続けており、週3日の勤務を楽しみにしていました。転倒による右肩前方脱臼を契機に、医師からは「高齢のため職場復帰は難しい」と伝えられていました。
しかし本人の「もう一度職場に戻りたい」という強い意欲を尊重し、医師の管理のもとで理学療法を開始しました。
初期評価
- ・ 可動域:屈曲90度、外転70度で制限と疼痛
- ・ 筋力:三角筋・腱板群ともに著明に低下
- ・ 生活動作:食事・書字は可能、上着の着脱に介助要
- ・ 職業動作:軽度の持ち上げ動作、両上肢を使う机上作業が困難
○高齢者の肩脱臼時のリハビリについて
1.関節保護と安心感の確立
まずは再脱臼を防ぐことが最優先です。
危険肢位を避け、サポーターを使用。肩甲骨周囲筋の動きを意識させながら、無理のない範囲での運動を開始しました。
2.筋力再教育
- ・ 初期は肘や手首を使った動作練習を通じ、間接的に肩周囲筋へ刺激を与えました。
- ・ 徐々にセラバンドを用いた内外旋運動を導入し、腱板筋群を段階的に強化。
- ・ 日常生活動作(食器を棚に戻す、書類を取り出す)を模した練習を行い、実生活に直結させました。
3.職業動作への応用
工房での作業に必要な「持ち上げ」「机上での物品移動」を想定し、リハビリ室内で再現。
重量物ではなく軽い素材から始め、姿勢や関節角度を細かく調整しました。
4.段階的な復職支援
- ・ まずは施設内で模擬作業を行い、疲労度や痛みを確認。
- ・ 主治医と連携し「短時間勤務」から再開。
- ・ 数か月後には週3日の勤務に復帰し、同僚との交流も回復しました。
○回復を支えた要因
1.本人の強い社会参加意欲
「職場に戻る」という具体的な目標が、リハビリ継続のモチベーションとなりました。
2.理学療法士による専門的判断
解剖学的に危険な動作を避けつつ、必要な筋群を的確に刺激できたことが、回復を安全に導きました。
3.職業動作への段階的アプローチ
単なる関節運動にとどまらず、実際の作業内容を想定した練習が復職の決め手となりました。
○理学療法士の役割
肩脱臼後の高齢者にとって、職場復帰は容易ではありません。しかし、理学療法士は以下の専門性を発揮することで可能性を広げられます。
- ・ 解剖学的理解:肩の安定構造と危険肢位を熟知し、関節を保護。
- ・ 障害学的理解:高齢特有の筋力低下やバランス能力を考慮し、安全な負荷設定を行う。
- ・ 生活・職業連携:日常動作の改善を職業上の課題へ発展させ、社会参加を最終ゴールに設定する。
◎「もう働けない」と諦めないためにリハビリを
高齢者の肩脱臼は、従来「生活レベルの維持」に留まるリハビリが主流でした。
しかし、適切なプログラムと本人の意欲があれば、職場復帰というより高い目標の達成も十分に可能です。
今回の症例は、理学療法士が専門的知識をもとに「関節の保護」と「筋力の再建」を両立させ、日常生活を越えて社会活動へとつなげた好例といえます。
「もう働けない」と諦めるのではなく、正しいリハビリを積み重ねれば再び自分の役割を果たすことができる──それこそが理学療法士が伝えるべき最大のメッセージなのです。