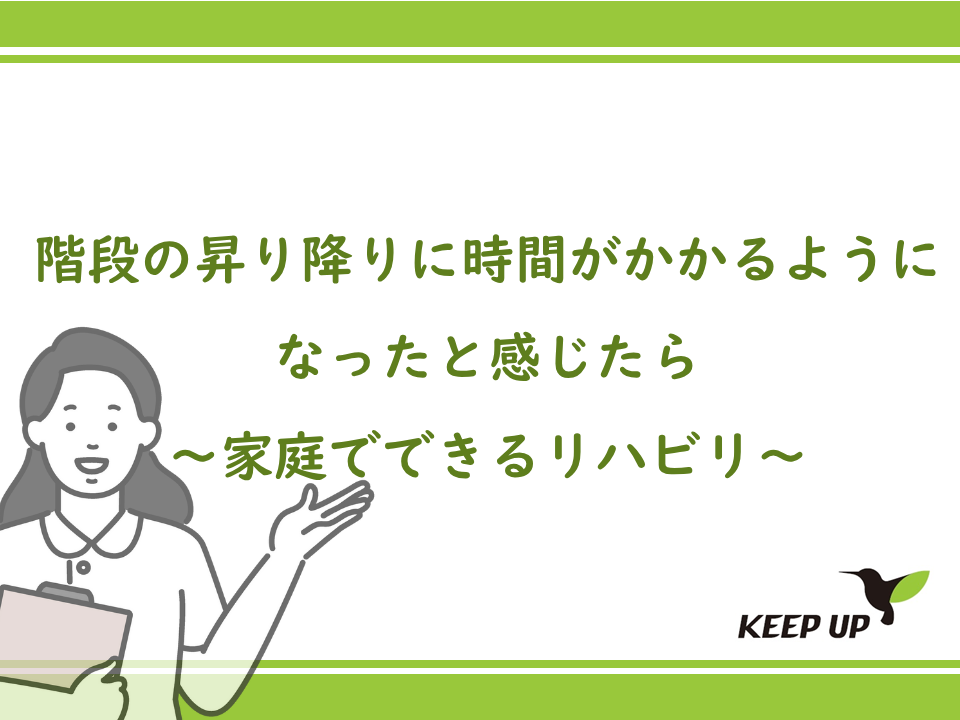「階段を上がるのに前より時間がかかる」「降りるのが遅くなった」「手すりがないと不安」――そんな変化は、高齢者にとって足腰の衰えを示す大切なサインです。
1.脊柱起立筋
背中をまっすぐに保つ筋肉で、階段を上るときに体幹が前に倒れすぎないよう支えます。姿勢を保てないと、足に力をうまく伝えられません。
2.大殿筋
お尻の筋肉で、股関節を伸ばす働きを持ちます。体を段差の上に持ち上げる主役であり、衰えると一段上がる動作が重く感じられます。
3.ハムストリングス
太ももの裏の筋肉で、股関節の伸展と膝の安定に関与します。階段を下りるときにはブレーキ役として働き、転倒予防に重要です。
4.下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)
ふくらはぎの筋肉で、つま先で体を押し出す力を生み出します。階段の最後の一歩をスムーズに上がるために欠かせません。これらの筋肉がバランスよく機能することで、階段を安全かつ効率的に昇り降りできるのです。
専門施設に通わずとも、日常生活に取り入れられる簡単な運動が数多く存在します。ここでは代表的なものをいくつか紹介しましょう。
○家庭でできる階段動作に必要なリハビリ サポート
理学療法士の視点から、主要抗重力筋を効率的に動かす運動を紹介します。
1.椅子からの立ち座り(大殿筋・ハムストリングスの強化)
- ・椅子に腰掛け、手を使わずに立ち上がる→ゆっくり座る。
- ・10回×2セット。
- ・階段を上るための股関節と膝の伸展力を養います。
2.かかと上げ(下腿三頭筋の強化)
- ・壁や手すりにつかまりながら、かかとを持ち上げてつま先立ち。
- ・15回×2セット。
- ・昇段時の蹴り出しが安定します。
3.体幹伸展運動(脊柱起立筋の活性化)
- ・椅子に座り、両手を胸に組んで、背筋を伸ばす動きを意識。
- ・10回程度。
- ・姿勢保持力を高め、階段動作全体を支えます。
4.ステップ練習(複合的トレーニング)
- ・低い段差に片足を上げ、体重を移動して下りる動作を繰り返す。
- ・実際の階段動作に近く、バランスと筋力を同時に強化。
○安全なリハビリに取り組むための注意点
- ・必ず安定した家具や手すりのそばで行う。
- ・無理な回数にこだわらず「疲れる前にやめる」ことが大切。
- ・痛みや強い不安を感じたら中止し、専門職に相談する。
○家族ができるサポート
「最近、階段が遅いね」と直接伝えると、ご本人は落ち込むことがあります。声かけは「一緒に運動してみよう」「この段差で練習してみる?」と前向きな表現を心がけましょう。ご家族が伴走者となることで、安全性も高まり、継続する意欲も維持できます。
◎サインに気付いたらリハビリ開始の検討を
階段の昇り降りが「遅くなる」「時間がかかる」という変化は、主要抗重力筋の筋力低下やバランス機能の衰えを示す重要なサインです。しかし、このサインに気づいた時点で家庭でのリハビリを始めれば、改善の余地は十分にあります。
脊柱起立筋・大殿筋・ハムストリングス・下腿三頭筋を意識した運動を日常に取り入れることで、階段動作だけでなく歩行全体の安定性も高まります。
「遅くなった」と感じたその時こそ、生活の質を取り戻す第一歩。ぜひ家庭での取り組みをスタートしてみましょう。