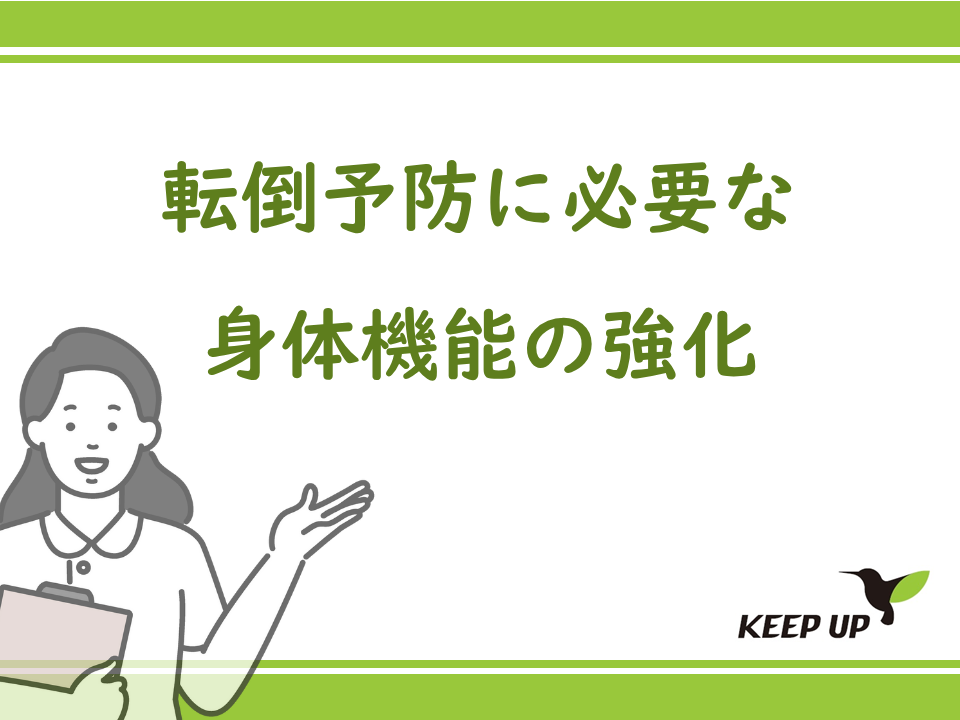高齢者の転倒。家族としては心配ですよね。転倒は怪我だけでなく、寝たきりや認知症につながる可能性も。転倒を繰り返すようでしたら、今こそ転倒予防に取り組む時です!
実は、バランス能力、柔軟性など身体機能を適切に鍛えることは、転倒リスクを減少するための方法として有効です。ここでは転倒予防に必要な身体機能の改善について、専門家の知見をもとに、ご家庭でも実践できる方法をお伝えします。大切なご家族の健康と自立した生活を守るために、今日から始めてみませんか?
◎転倒予防のための身体づくりは運動から
「転倒を予防するためには、運動が大切です!」
運動が大切? 具体的には転倒しない身体づくりのためです。
運動が大切となんとなくは分かっていても、どうして運動が必要なのか、なぜ運動が予防に繋がるのか。高齢者の転倒が起きる原因を知り、身体機能について考えてみましょう。
◎転倒が起きる背景
転倒予防白書2019によると、転倒に影響する重要因子として危険度順に以下のように挙げられています。
① 筋力低下
② 転倒歴
③ 歩行障害
④ バランス障害
⑤ 装具(杖)使用
⑥ 視力障害
⑦ 関節炎
⑧ ADL障害
⑨ 抑うつ
⑩ 認知機能障害
⑪ 年齢80歳以上
転倒率については、このうち1つだと10%程度ですが、4つ以上重なると…なんと70%以上、とされています。
また、転倒歴として過去1年間に起きた転倒が、その後の転倒についての高い因子となっていることも注目すべきことです。
身体機能に関連する(疾病によるものではない)転倒は、加齢に伴うさまざまな機能の低下によるものと考えられます。
一方で加齢に伴う身体機能については、継続的なトレーニングや訓練によって機能の低下を予防すること、そして機能の強化を図ることができるのです。
身体機能は変化させることができる。…ということは、重要因子のうち危険度として上位にある、
① 筋力低下
② 転倒歴
③ 歩行障害
④ バランス障害
については、機能を変化・改善させることで、「予防と強化ができる」と考えることができます。
これは、とても大きな意味を持つことです。
◎身体機能を変化・改善させるには
筋力は加齢に伴い低下します。
一般的に、30代でピークに達し、その後は毎年約2,3%低下、60代以降は急激な低下となりますが低下の程度は日常生活の中での活動量に左右されるとされています。
つまり、30代以降は何もしなければ筋力は落ちていく一方ということになります。そこで、運動により筋力の低下を防ぐ=筋力の維持や向上に繋げることが、身体機能の改善に効果的、ということになります。
転倒予防のためには主に足や腰、腹部の筋力やバランス能力をアップし、歩行能力向上を目指すトレーニングが効果的です。
ここでのトレーニングとは激しいものである必要はなく、年齢や体力、健康状態に応じて無理のない範囲で安全を確保しながらできること、そして習慣化することが大切です。
それでは、今日から簡単にできるトレーニングをひとつご紹介します。
~転倒予防トレーニング~
準備:椅子に浅めに座り、肩幅の広さで足裏全体を床につけます。座ったまま行います。(椅子からずり落ちないよう注意しましょう。)
『つま先上げ』
踵を床につけたまま、「つま先を出来るだけ高く上げる→ゆっくり下げる」を繰り返す
…脛の筋肉を鍛えます。つま先を上がりやすくすることで、つまずきを予防します。
『かかと上げ』
つま先を床につけたまま、「かかとを出来るだけ高く上げる→ゆっくり下げる」を繰り返す。
…ふくらはぎの筋肉は、人体で最も強力な腱「アキレス腱」とつながっており、歩くときに地面を力強く“けり出す”推進力を生み出す重要な役割を果たします。さらに、ふくらはぎやすねの筋肉は、立っているときに姿勢を保つ「抗重力筋」としても働いています。ふくらはぎは「第二の心臓」と言われ血液を心臓に戻すポンプ作用をするため非常に大切な筋力です。
『足踏み』
おなかに力を入れて膝を高く上げることを意識し、腕を振りながら足踏みします。
◎運動習慣が高齢者の転倒を予防する!
高齢になれば身体機能の低下は仕方がない…
諦めて放っておくと、どんどん身体機能は低下してしまい、転倒の危険性が高まります。
運動することで身体機能の低下を防ぎ、改善させることで、転倒予防に繋げましょう!